はじめに
土地探しを始めると、必ず出てくる「用途地域」という言葉。不動産サイトや資料に小さく書かれていても、「なんのことかよく分からない…」という方も多いのではないでしょうか?
でも実は、この「用途地域」は、建てられる建物の種類や将来の暮らし・資産価値にまで影響する重要なルールです。
今回は、一級建築士の目線から、用途地域とは何か?なぜ重要なのか?どんなことに気をつけるべきか?初心者にもわかりやすく解説していきます。この記事では、まず用途地域の基本概念を理解し、次に13種類ある用途地域の特徴、そして資産価値への影響まで順を追って説明していきます。土地選びの失敗を避けるための重要な知識となりますので、ぜひ参考にしてください!

用途地域ってなに?ざっくり一言でいうと…
「このエリアには、どんな建物を建てていいか」を定めたルールです。都市計画法と建築基準法に基づいて定められており、全国の市区町村が地域ごとに指定しています。
例えば、
- 住宅街には「静かな暮らし」を守るために高層ビルや工場はNG!
- 商業エリアではお店やオフィスOK、住宅も可能
- 工業エリアでは住宅NGの場所もある
このように、「建物の用途」をコントロールして、安心・快適な街づくりをするための仕組みなのです。
用途地域の基本を理解したところで、次は13種類ある用途地域の具体的な内容を見ていきましょう。
✅ 用途地域の知識を活かして「どんな土地を選ぶべきか」具体的に知りたい方はこちら
失敗しない土地選びのポイント|建築士が教えるマイホームの土台の選び方
13種類の用途地域一覧
用途地域は、以下の13種類に分類されています:
住居系(静かな住環境を守る)
- 第一種低層住居専用地域:一戸建てや小規模な共同住宅が中心
- 第二種低層住居専用地域:小規模な店舗や事務所も可能
- 第一種中高層住居専用地域:中高層マンションが建てられる
- 第二種中高層住居専用地域:中規模な店舗や事務所も可能
- 第一種住居地域:大きめの店舗やホテルなども立地可能
- 第二種住居地域:カラオケなど一部の娯楽施設も可能
- 準住居地域:自動車販売店なども立地可能な住宅地
商業系(店舗・オフィスが多い)
- 近隣商業地域:日常の買い物施設が集まる地域
- 商業地域:オフィスや大型商業施設が立ち並ぶ地域
工業系(工場や作業場が多い)
- 準工業地域:住宅と小規模工場が混在する地域
- 工業地域:大きな工場が建つ地域(住宅も可能)
- 工業専用地域:工場のみが許可される地域(住宅は不可)
その他
- 田園住居地域:農地と住宅が調和した地域(2018年に新設)
用途地域の種類を理解したところで、次は具体的にどのような制限があるのか詳しく見ていきましょう。
用途地域で何が決まるの?
主に以下のことが制限されます:
| 内容 | 具体的な制限内容 |
|---|---|
| 建てられる建物の種類 | 住宅、店舗、工場、病院、学校など |
| 建ぺい率・容積率 | 敷地面積に対する建物の大きさ |
| 高さ制限・斜線制限 | 日照・景観への配慮 |
| 騒音やにおい | 工場や娯楽施設の可否 |
建築士のひとこと:
土地の「広さ」や「価格」だけを見て選ぶと失敗します。“何を建てられるか”が決まっているからこそ、用途地域の確認は最優先。
では次に、用途地域がどのように資産価値や暮らしに影響するのか、実践的な視点で解説していきます。
資産形成・暮らしの視点から見る「用途地域」
①住居系は将来も”暮らしやすさ”を守ってくれる
→高層ビルやパチンコ店などが建ちにくい
→静かで資産価値が安定しやすいエリア
特に第一種低層住居専用地域は最も厳しく住環境が守られており、戸建て住宅を建てる場合は、長期的な住環境の安定性を考慮するとおすすめです。ただし、コンビニなどの生活利便施設が建てられない場合もあるため、立地とのバランスも重要です。
資産価値の傾向:
住居系の用途地域、特に第一種低層住居専用地域は、景気変動の影響を受けにくく、資産価値が安定する傾向があります。東京23区内では、高級住宅街の多くがこの用途地域に指定されており、土地価格の下落率も他の用途地域より小さいケースが多いです。
②商業系は利便性◎。でも騒音・人の流れには注意
→駅近や繁華街が多く、将来の売却や賃貸ニーズは高め
→一方で、ファミリー層には落ち着かないことも
商業地域や近隣商業地域は、利便性の高さから不動産価値が上がりやすい傾向にあります。投資目的なら検討価値が高いですが、居住目的なら夜間の騒音や人通りなどの生活環境をよく確認しましょう。
資産価値の傾向:
商業地域は景気の影響を受けやすく、好景気時には急上昇し、不景気時には下落することがあります。特に「再開発計画」がある地域では価値が大きく上昇することも。一方で、シャッター商店街のような衰退した商業地域は価値が下がり続けることもあるため、周辺の発展性も重要なチェックポイントです。
③準工業地域は価格が安い反面、リスクも
→工場や大型施設が近くにある可能性
→資産価値のブレが大きいため、慎重な検討が必要
準工業地域は比較的土地価格が安く、建築の自由度も高いのがメリットです。ただし、将来どんな建物が隣接するかわからないリスクもあります。周辺環境をよく調査し、将来的な地域の発展性も考慮しましょう。
メリットとリスクのバランス:
準工業地域は他の用途地域と比べて20〜30%程度土地価格が安いことが多く、広い土地を手に入れられる可能性があります。また、店舗併用住宅や小規模な工場など、多様な建物が建てられる自由度の高さも魅力です。隣地に好ましくない施設が建つリスクは、周辺環境の徹底調査やリスクヘッジ(例:緩衝緑地帯を自分の敷地内に設ける)で軽減できる場合もあります。
④工業地域・工業専用地域は住宅地としては要注意
→工場や倉庫が建ち並ぶエリアで、環境変化のリスクが高い
→住宅用地としては、特別な理由がない限り避けた方が無難
特に工業専用地域は住宅が建てられないため、土地活用の選択肢が限られます。工業地域は住宅建築も可能ですが、24時間操業の工場が建つ可能性もあり、居住環境としては厳しい面があります。
活用メリットとリスク軽減策:
工業地域は土地価格が最も安価(住居系の40〜60%程度)で、将来の用途変更による価値上昇の可能性を見込んだ長期投資としての選択肢もあります。実際に、かつての工業地域が再開発によって高級マンションエリアに変わった例も各地にあります。ただし、これは投資的な視点であり、実際に居住する目的なら、工業地域は避けるのが無難です。
用途地域別に建築できる主な建物一覧
用途地域ごとに建てられる代表的な建物を表にまとめました。土地選びの参考にしてください。
| 建物の種類 | 第一種低層住居専用 | 第一種住居 | 近隣商業 | 商業 | 準工業 | 工業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て住宅 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中高層マンション | △(高さ制限あり) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| コンビニ・小型店舗 | △(条件付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大型スーパー | × | △(条件付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| オフィスビル | × | △(小規模のみ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| パチンコ店・風俗店 | × | × | △(条件付き) | ◯ | △ | △ |
| 工場(小規模) | × | △(条件付き) | △ | △ | ◯ | ◯ |
| 工場(大規模) | × | × | × | △ | ◯ | ◯ |
※この表は一般的な目安です。具体的な制限は自治体の条例によって異なる場合があります。
✅ 土地の条件だけでなく「予算配分」も家づくり成功のカギです
建築士が語る!理想の家をつくるために必要な費用とは?|予算設計から資産形成まで徹底解説

Q&A:よくある質問
Q. 用途地域はどうやって調べればいい?
→市区町村の「都市計画図」や、国交省の「国土交通省 都市計画基礎調査情報システム」で確認可能です。また、不動産会社や建築士に聞けば教えてくれます。物件資料には必ず記載されているはずなので、不明点は積極的に質問しましょう!
Q. 用途地域って変更されることはある?
→大きな都市計画変更がない限り、基本的には数十年単位で固定です。ただし再開発などの可能性もあるため、「将来の計画」もチェックすると安心です。市区町村の都市計画課で「都市計画マスタープラン」を確認すると、将来的な方向性がわかります。
Q. 同じ用途地域でも地域によって雰囲気が違うのはなぜ?
→用途地域は最低限のルールであり、各自治体が独自の「地区計画」や「建築協定」を設けていることがあります。これにより、より細かく建物の高さや外観、用途などが制限されている場合があります。土地購入前に、これらの上乗せ規制の有無も確認しておくと安心です。
Q. 用途地域が合わない場合、変更申請はできる?
→個人で用途地域の変更申請をすることは実質的に困難です。用途地域の変更は、自治体が都市計画全体を見直す際に行われるもので、個人の希望では変更されません。ただし、建物の用途については「用途許可制度」という特例を申請できる場合があります。これは非常に限定的ですが、公益性が認められる場合など、特定の条件下では認可されることもあります。
実体験:将来の価値を左右する用途地域の話
過去に「工業地域の端の土地で戸建てを建てた施主さん」が、「周りに工場が増えて子どもが遊びにくくなった」と相談に来たことがあります。
土地価格が安かった分、建物にお金をかけられたけれど、将来の”暮らしやすさ”や”資産性”まで考えておくべきだったと話されていました。
この事例から学ぶ解決策:
- 工業地域で住宅を検討する場合は、周辺の将来計画を徹底的に調査する
- 市役所で「工場立地計画」や「企業誘致計画」がないか確認する
- すでに住んでいる方なら、防音・防振対策、緑化による視覚的な緩衝などの対策が可能
- 子育て世帯の場合、学区の変更申請が可能な地域もあるため、教育委員会に相談する方法もある
また別のケースでは、「第一種低層住居専用地域」で静かな環境を求めて家を建てたものの、「近くにコンビニが建てられない」「商店街が遠い」という不便さに後悔したという方もいらっしゃいます。規制が厳しい分、生活利便性とのバランスを考慮することも大切です。
この事例から学ぶ解決策:
- 生活利便施設へのアクセスを重視する場合は、第二種低層住居専用地域など、少し緩やかな規制の地域も検討する
- 自家用車の所有や、最寄り駅からの距離など、日常の買い物導線を事前にシミュレーションする
- 将来的に近隣に商業施設が建つ可能性(空き地の有無や開発計画)も調査しておく
用途地域と再開発による資産価値変動の実例
用途地域の変更や再開発により、土地価格が大きく変動した実例をいくつか紹介します。
上昇事例
- 東京都江東区豊洲地区 工業地域から商業・住居系へ用途変更され、大規模再開発により地価が約3倍に上昇。
- 横浜市みなとみらい地区 かつての工業地域が商業・業務地区へと変貌し、周辺地価が20年間で2倍以上に。
下落事例
- 地方都市の旧商店街 近隣への大型ショッピングモール出店により、古い商業地域の地価が10年間で30%以上下落。
- 工場移転後の工業地域 主要工場の海外移転後、関連企業も撤退し、土地需要減少で地価が大幅下落。
このように、用途地域は土地の将来価値を見極める重要な指標になります。特に「将来の都市計画」や「再開発計画」の有無は、資産価値に大きく影響するため、土地選びの際には必ずチェックしましょう。
まとめ
- 用途地域=土地に建てられる建物のルール
- 暮らしやすさ・建築制限・資産価値に直結する重要な要素
- 土地探しでは「広さ・価格」だけでなく、「用途地域」を必ずチェック!
- 自分のライフスタイルに合った用途地域を選ぶことが大切
- 長期的な資産価値を考慮し、地域の将来性も調査することが重要
この記事では、用途地域の基本から資産価値への影響、実際の選び方まで紹介してきました。土地選びは人生の大きな決断です。用途地域という「見えないルール」を理解することで、後悔のない選択ができるよう願っています。
建築士としてのアドバイス: “今”だけでなく”10年後・20年後”の視点で土地を選ぶことで、後悔のない家づくり・資産形成が実現できます。用途地域は土地選びの最重要チェックポイントの一つです!
関連記事
✅ 土地が決まったら、次は「どこに建ててもらうか」も重要です

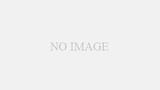
コメント