はじめに
「投資って儲かったら税金かかるの?」「NISAなら非課税って聞いたけど?」
投資を始めると、意外とすぐに出てくるのが”税金の疑問”です。せっかく増やしたお金も、税金の仕組みを知らないだけで損をしてしまうことも…。
この記事では、投資初心者が知っておくべき税金の基本と非課税制度をわかりやすく整理します! 建築士として資産形成に取り組む立場から、「家+お金」の両面で失敗しないための考え方も合わせてお伝えします。

投資利益にかかる税金の基本
1. 株・投資信託の利益には「20.315%」の税金
株式譲渡益や配当金にかかる税率は以下の通りです:
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:0.315%
合計で20.315%の税金がかかります。これは「申告分離課税」と呼ばれる方式で、他の所得と分離して計算されます。
注意: 2024年現在、金融所得課税の見直しが議論されていますが、まだ実施されていません。今後の税制改正に注目しましょう。
2. 年間利益が出れば、自動で税金が引かれる
特定口座(源泉徴収あり)を選べば確定申告は不要です。ただし、損益通算や繰越控除を利用する場合は申告が必要になります。
税金知識を知ったあとは、実際に「何をどう申告するか」も学んでおきましょう
投資初心者向け 確定申告の超基本|建築士が解説!申告の必要なケースと見落としがちなポイントとは?
非課税制度の活用が”初心者の守り”になる
1. NISA(新NISA)
2024年からスタートした新NISA制度の主な特徴は以下の通りです:
- 非課税枠:年間360万円(成長投資枠120万円+つみたて投資枠120万円)
- 非課税保有限度額:1,800万円
- 非課税保有期間:無期限化
これにより、長期的な資産形成にも適した制度となっています。
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 拠出金は全額所得控除対象=節税効果◎
- 運用益も非課税で再投資可能
- 受け取り時には「退職所得控除」や「公的年金控除」が適用されます
老後資産形成と節税効果を両立できる制度として活用価値があります。
利益を守るには“税制優遇制度”の活用が超重要!↓
【2025年版】NISAとiDeCoの違いを徹底解説!初心者でもわかる選び方ガイド
意外と見落とされがちな税金のケース
1. 損失が出たら「損益通算」できる
株式や投資信託で損失が出た場合、他の利益と相殺することで税負担を軽減できます。さらに、損失額が大きい場合は翌年以降3年間繰越控除を利用できます。
ただし、NISA口座で発生した損失は損益通算や繰越控除の対象外なので注意しましょう。
2. 配当金は「総合課税」「申告分離課税」の選択も可能
所得が少ない場合、総合課税で所得控除を受けられるケースがあります。収入状況によってどちらを選ぶべきか変わるため注意しましょう。
特に、年収が低い場合や基礎控除・社会保険料控除などの所得控除が大きい場合は、総合課税のほうが税負担が少なくなる可能性があります。
建築士×資産形成の視点:家計と税金を「一体設計」する
住宅ローン控除や保険料控除なども”節税対策”になります。投資の利益と節税ポイントを把握することで、家計全体で効率的な資産形成につながります!
資産形成は「増やす力」だけでなく、「守る力(税金知識)」も欠かせません!
“家族で投資”を考えるなら、税金のことも含めた戦略が必要です
夫婦で投資を始めるときの失敗しないルール|建築士が実践する”家と資産”を守る共同戦略

Q&A:よくある質問
Q. 利益が20万円以下なら税金はかからない?
A. 「給与以外の所得が年間20万円以下なら申告不要」というルールがあります。ただし、特定口座(源泉徴収あり)では自動的に課税されるため注意しましょう!もし申告することでメリットがある場合(損益通算や配当の総合課税選択など)は、20万円以下でも確定申告をすることができます。
Q. NISAとiDeCo、両方使っていいの?
A. もちろんOK!併用することで非課税の恩恵を最大化できます。ただし、iDeCoは60歳まで引き出せない点には注意してください。また、拠出金の上限は職業によって異なります(会社員なら月額2.3万円まで、自営業なら月額6.8万円までなど)。
実体験:税金の知識で「損しない投資」ができた話
ある20代投資初心者は年間10万円ほど利益を得ましたが、損益通算やNISA活用を知らずに余計な税負担をしてしまった経験があります。具体的には、Aという株で5万円の利益、Bという株で3万円の損失が出ていました。
特定口座(源泉徴収あり)だったため、Aの利益には約1万円の税金が引かれましたが、損益通算を知らなかったためBの損失が活かされませんでした。
その後、税金の知識をつけてNISA口座を開設し、長期投資商品はNISAで購入。さらに特定口座内での損益通算も活用するようになったところ、同じ投資額でも手取り額がアップしました!
「知らないと損する」と学んだ実体験です。
まとめ
- 投資には利益とセットで「税金」がついてくる。だからこそ知識は”防御力”!
- NISA・iDeCo・損益通算など初心者向け制度は豊富。
- 建築士×資産形成では、「家計設計に税金知識」を組み込むことで将来の損得が大きく変わります。
税金の仕組みを知ることは、投資収益率向上への第一歩です!
関連記事
準備中。。

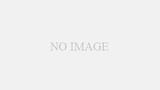
コメント