はじめに
「子どもが大学進学で家を出た」「就職して別の都市に引っ越した」「結婚して独立した」――そんな子どもの巣立ちを経験し、「この広い家、これからどう活用していこうか?」と悩むご家庭も多いのではないでしょうか?
私の建築士事務所にも、「子どもが独立して夫婦二人だけの生活になった」「定年退職後の住まい方を考え直したい」というご相談が増えています。特に50代後半から60代のお客様からは、「今の家を終の棲家にするか、住み替えるか」という悩みをよく聞きます。
人生100年時代、老後の暮らし方も多様化しています。住宅はただの「住まい」ではなく、「人生を支える資産」として活用できる時代になりました!
本記事では、建築士としての視点×資産形成の視点から、「子どもが巣立った後の家をどう活用すべきか?」「将来も柔軟に使える間取りとは?」について、実体験も交えながらわかりやすくお伝えしていきます。

子どもの独立後に多い住まいの悩みとは?
空いた部屋、広すぎる家、将来への不安など、多くの方が経験する悩みをまとめました:
- 子ども部屋が空き部屋になってしまった
- 家が広すぎて掃除や管理が大変になった
- 二世帯や同居を検討していたが現実的でなかった
- 将来的に売却・賃貸できる家なのか不安がある
こういった悩みは、家を「資産」として捉え直すことで解決策が見えてきます。
資産価値を落とさない!将来を見据えた間取りのポイント
将来も価値が下がりにくい住まいづくりには、以下のポイントが重要です:
1. フレキシブルな間取り設計
可動式の間仕切りや、将来的に壁を取り払えるような構造設計を取り入れると、ライフスタイルの変化に合わせて空間を変えられます。例えば、子ども部屋と子ども部屋の間の壁を後から取り外せるようにしておくと、将来は広いリビングや趣味の部屋として活用できます。
2. 二人暮らしになっても快適な動線設計
家族が減っても暮らしやすい動線を意識しましょう。特に寝室からトイレ・浴室へのアクセスは年齢を重ねるほど重要になります。一階に寝室・浴室・トイレ・キッチン・リビングがコンパクトに収まる設計なら、将来的にも安心です。
3. 老後のバリアフリー化を視野に入れる
後からでも対応できるよう、廊下や開口部は少し広めに設計しておくと良いでしょう。また、玄関や浴室など段差が生じやすい場所は、将来的な改修を見越した構造にしておくことがポイントです。
4. リフォーム・リノベーションのしやすさ
耐震等級の高い構造や、梁や柱の配置に余裕を持たせた設計にすると、将来のリフォームの自由度が高まります。特に水回りは変更コストが高いため、将来の変更を想定した配管設計が重要です。
5. 一部を賃貸できる分離構造
二世帯住宅のような分離可能な構造にしておくと、将来的に一部を賃貸に出したり、介護スペースとして活用したりできます。別々の出入り口や水回りがあれば、活用の幅が広がります。
建築士の立場から見ても、「将来に応じて住み替えずに済む設計」は、長期的なコスト削減&資産価値維持につながります。
家を「資産」として考える具体的メリット
住宅を単なる「住む場所」ではなく「資産」として考えると、さまざまな可能性が見えてきます。
賃貸収益の実例
都市部の戸建て住宅の場合、一部を賃貸に出すことで月額5〜10万円の収入を得ることも可能です。例えば、東京郊外で築15年の戸建て住宅の1階部分(約30㎡)を改修して賃貸化したケースでは、改修費用150万円の投資で月額8万円の家賃収入を得ることに成功しています。投資回収期間は約19ヶ月という計算になります。
資産価値が下がりにくい住宅の特徴
不動産市場データによると、以下の特徴を持つ住宅は資産価値が維持されやすい傾向があります:
- 駅から徒歩10分以内の立地
- 耐震等級2以上の構造性能
- 断熱等級4(2022年基準)以上の省エネ性能
- 間取りの汎用性(3LDKなど一般的な間取り)
- メンテナンス状態の良さ
特に最近は「省エネ性能」への注目度が高まっており、高断熱・高気密の住宅は中古市場でも評価される傾向にあります。国土交通省の調査によれば、断熱等級4の住宅は断熱等級1の住宅と比較して、中古市場で約10〜15%高い価格で取引される傾向があります。

実体験:親の家づくりで感じた”後悔”と”学び”
私の両親は20年前に建てた家で、今こんな課題に直面しています:
後悔した点:
- 二階に4つもあった子ども部屋が完全な空き部屋になり、掃除や管理が負担に
- 和室を作ったものの、現代的な生活では使わなくなってしまった
- 断熱性能を重視せず、高齢になった今、冬の寒さが体にこたえるようになった
技術的な課題と解決策:
特に断熱性能の問題は深刻で、築20年の住宅のため断熱等級は旧基準の「等級2」相当です。これは現在の基準(等級4)と比較して、約2倍のエネルギー消費につながっています。両親の家では、冬場の室温が16℃を下回ることも多く、ヒートショック対策としても危険な状態でした。
解決策としては以下の選択肢がありました:
- 全面的な断熱リフォーム:約350万円の費用がかかるが、光熱費削減と快適性向上で長期的には回収可能
- 部分的な断熱改修:居室だけを断熱改修(約150万円)し、使用頻度の低い部屋は閉鎖して冷暖房効率を上げる
- 住み替え:断熱性能の高い中古マンションへの住み替え(売却と購入の差額約500万円)
最終的に両親は2番目の「部分的な断熱改修」を選択し、1階のみを集中的に断熱改修しました。2階は基本的に使用せず、来客時のみ開放する方針に変更し、エネルギー効率と管理負担の両方を改善できました。
学んだこと:
- 将来の家族構成の変化を想定した可変性のある間取りの重要性
- 年齢を重ねても快適に過ごせる一階中心の生活動線設計
- 売却や賃貸を視野に入れた、一般的な間取りの採用
- 長期的な住宅性能(特に断熱性能)への投資は、将来の住みやすさと資産価値維持の両方に効果がある
これらの経験から、私は自分のクライアントには「10年後、20年後の暮らし方」を必ず想像してもらい、その上で間取り提案をするようにしています。また、初期コストを少し上げてでも断熱性能や可変性の高い設計を勧めることが増えました。
よくある質問に答えます
Q1. 子どもが使っていた部屋はどう活用すればいい?
A. まずは家族の趣味や関心に合わせた活用がおすすめです。書斎、ホームジム、ゲストルーム、作業部屋など。さらに将来的には民泊や賃貸としての活用も検討できます。例えば、2つの子ども部屋を繋げて広いワークスペースにする方も増えています!
空き部屋活用で特に人気なのは:
- 在宅ワークスペース:コロナ以降、需要が急増したホームオフィス。Web会議用の背景や照明にこだわる方も多いです。
- 趣味特化型ルーム:楽器演奏、ハンドクラフト、ホームシアターなど、音や匂いを気にせず楽しめる専用空間。
- ゲストルーム兼収納:普段は収納スペースとして活用し、来客時にはベッドを出して宿泊スペースに変身させる多機能部屋。
Q2. 今から間取り変更って大変?
A. 実は「水回りを動かさなければ」意外と簡単に変更できます。壁の撤去や新設は100万円前後から可能です。ただし、キッチンや浴室などの水回りを移動させる場合は300万円以上かかることも。まずは建築士や住宅リフォーム会社に相談してみましょう。
Q3. リフォーム費用を抑える工夫はありますか?
A. リフォーム費用を抑えるポイントはいくつかあります:
- DIYで可能な部分は自分で行う:壁紙の張り替えや簡単な塗装作業は、DIYで行うことで30〜50%のコスト削減が可能です。
- 補助金や税制優遇を活用する:省エネリフォームなら最大60万円の補助金が受けられる制度や、バリアフリーリフォームの減税制度があります。
- フルリフォームではなく部分リフォームを検討する:特に劣化が気になる部分だけを改修することで、全面改修の1/3程度の費用で済むことも。
- 適切な時期を選ぶ:建設業界の閑散期(12〜2月頃)はリフォーム業者も比較的空いており、割引プランを提示してくれることがあります。
Q4. 賃貸活用時に必要な手続きや注意点は?
A. 自宅の一部を賃貸にする場合、以下の手続きや注意点があります:
- 法的手続き:住宅の用途変更申請(必要な場合)、賃貸借契約書の作成、固定資産税の住宅用地特例の見直しなど
- 保険の見直し:火災保険を「賃貸物件用」に変更する必要があります
- 税金の考慮:賃料収入は「不動産所得」として確定申告が必要(経費計上で節税も可能)
- 設備対応:専用メーターの設置、防音対策、プライバシー確保のための動線分離など
専門家(税理士、不動産管理会社)への相談がおすすめです。初期投資は必要ですが、適切に設計すれば安定した副収入源になります。
Q5. 将来の売却を考えると、どんな点に気をつけるべき?
A. 一般的に売却しやすい住宅は、標準的な間取りとメンテナンス状態の良さが重要です。特殊な間取りや設備は個性的ですが、売却時には不利になることも。また、断熱性能や耐震性能の高さは近年の住宅購入者にとって重要なポイントになっています。特に若い世代は「住宅性能表示制度」の等級を重視する傾向があり、耐震等級や断熱等級が高い物件は平均で約5〜10%高く売却できるというデータもあります。
まとめ
- 子どもが独立した後の家も「人生後半のステージ」に重要な役割を果たします
- 家は”終の住処”でもあり、”活用できる資産”にもなります
- 柔軟な間取り設計や将来の用途を見据えた設計は、人生の安心材料になります
「住まいをどうするか=資産をどう活かすか」その視点を持つことが、これからの家づくりに欠かせません。将来を見据えた住まいづくりで、豊かなセカンドライフを実現しましょう!
関連記事
✅ 巣立ち後の暮らしに合わせて「建て替え or リフォーム」の視点も持っておきましょう
✅ 間取りを考えるとき、“将来のコスト”も含めて考えてみませんか?
建築士が語る!理想の家をつくるために必要な費用とは?|予算設計から資産形成まで徹底解説
✅ 将来、間取りに後悔しないために。“よくある失敗例”から学んでおきましょう

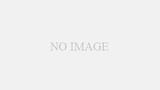
コメント