はじめに
建築士として、これまで何十棟もの家づくりに関わってきました。その中で「この仕様は羨ましいな」「これはやめておいた方がいいな」と、たくさんの”リアル”を見てきました。
じゃあ、自分が将来マイホームを建てるなら?プロとして、そして生活者として、ここだけは絶対に妥協しないというポイントがあります。
この記事では、建築士のリアルな目線で、「これだけは外せない5つのこだわりポイント」をご紹介します。家づくりを考えている方、現在進行中の方はぜひ参考にしてください!
① 採光と風通し:快適さの鍵
- 間取りや広さより先に考えるのが「光と風の質」
- 特に朝〜昼の自然光は、暮らしの満足度と体調に直結します
- 吹き抜け or 天窓/東西南北の開口バランスを徹底検討
住まいの快適さを決める最大の要素が「光と風」です。どんなに広い家でも、日当たりが悪く風が通らなければ、気持ちの良い暮らしはできません。逆に、コンパクトな家でも光と風を上手に取り込む設計なら、心地よく過ごせるのです。
特に重要なのは、朝日が入る東側の窓配置。朝の光は精神衛生上も体内時計のリセットにも重要で、寝室やキッチンには朝日が入るよう計画するのがおすすめです。また、夏の西日対策も忘れずに!
採光を確認する具体的な方法
- 無料アプリ「サンサーベイ」や「Sun Seeker」で太陽の軌道を確認
- Google Earthの日照機能を使って周辺建物の影響を把握
- 現地で朝・昼・夕方の3回、実際に光の入り方を確認(特に冬至前後が理想)
✅ 建築士メモ:日照シミュレーション&現地の日影確認は絶対やる!季節や時間帯による日当たりの変化をしっかり調査。特に冬至の日照時間は必ずチェックしましょう。
② 収納の質:使いやすさが決め手
- とにかく収納多め…はNG。配置・動線・奥行きが命です
- 土間収納/パントリー/WICの落とし穴とは?
- 収納の作り方次第で、生活感の出方が変わる=美観の差に直結します
「収納は多ければ多いほど良い」と思っていませんか?実は、単に量を増やすだけでは逆効果になることも。重要なのは「必要なものを、必要な場所に、取り出しやすく」という原則です。
家族構成別・おすすめ収納計画
共働き夫婦の場合
- 玄関近くの土間収納(幅120cm×奥行60cm程度)で帰宅動線をスムーズに
- キッチン横のパントリー(奥行30〜40cm、幅90cm以上)で買い物袋をそのまま収納
- 洗面所近くのランドリークローゼットで洗濯〜収納の動線を短縮
子育て世帯の場合
- リビング内の低い収納で子どものおもちゃを自分で片付けられる工夫
- 成長に合わせて棚板の高さ調整ができるクローゼット
- ファミリークローゼットで家族全員の衣類をまとめて管理
✅ 建築士メモ:家族構成・将来の暮らしに合わせて「収納の成長性」も意識しましょう。子どもの成長、家族の趣味の変化など、将来のライフスタイル変化を想定した収納計画が大切です。
③ 素材選びで維持費削減
- 外壁・屋根・フローリング=メンテ費用がかかる代表格
- 初期コストより、10年後・20年後の維持費を見越して選ぶべき
- シーリングレス外壁、耐候性塗料、無垢材 or 高耐久フロア
家は「建てて終わり」ではなく、長く住み続けるほどメンテナンスコストがかかります。20年住むなら、建築費と同等のメンテナンス費用が必要という試算もあるほどです。
素材別メンテナンス比較表
| 素材・部位 | 初期費用 | メンテ周期 | メンテ費用 | 20年間総コスト |
|---|---|---|---|---|
| 一般塗装サイディング | 標準 | 10年ごと | 約100万円/回 | 約200万円 |
| シーリングレス外壁 | +30〜50万円 | 15〜20年 | 約80万円/回 | 約80〜130万円 |
| 一般屋根材 | 標準 | 10年ごと | 約80万円/回 | 約160万円 |
| ガルバリウム鋼板 | +20〜30万円 | 20年以上 | 約60万円/回 | 約60万円 |
| 複合フローリング | 標準 | 10〜15年 | 約50万円/回 | 約50〜100万円 |
| 高耐久フローリング | +10〜20万円 | 20年以上 | 約50万円/回 | 約50万円 |
✅ 建築士メモ:ランニングコストまで含めて「家計の長期計画」で考えましょう。初期費用を抑えるために安い素材を選ぶと、長期的には家計を圧迫することも。特に外壁・屋根・水回りは妥協せず、耐久性の高い素材を選びましょう。
④ 生活動線の工夫:家事ラク設計
- 毎日の動きやすさ=暮らしの快適さに直結します
- 脱衣所⇔洗濯⇔干す⇔しまうの流れがスムーズか?
- ゴミ出し・帰宅動線・買い物収納の配置は全体設計に影響
家事の効率は、住まいの間取りによって大きく左右されます。特に重要なのは「水回りの動線」と「帰宅後の動線」です。例えば、洗濯物を洗う→干す→取り込む→たたむ→しまう、という一連の流れがスムーズにできるか考えてみましょう。
家事ラクを実現する具体的な間取りのポイント
- キッチン⇔パントリー⇔ダイニングが三角形の位置関係になるよう配置
- 洗面所と脱衣所は分けて、同時に使える設計に
- 玄関から洗面所までバッグや上着を持ったまま直行できる動線
- キッチンからゴミ置き場までの最短ルート確保
✅ 建築士メモ:モデルハウスより「自分たちの生活ルーティン」で間取りを考えましょう。朝の準備、帰宅後の行動、休日の過ごし方など、実際の生活パターンをイメージして間取りを検討することが重要です。
⑤ 余白の設計:変化に強い家
- あえて使い方を決めない「余白」が、未来の変化に対応できます
- 子どもが増えた/趣味ができた/副業スペースが必要…全部OKにできる空間
- 土地や間取りに「遊び」がある家は、資産価値も下がりにくい傾向があります
完璧に設計された家は、実は将来の変化に弱いことがあります。家族構成の変化、働き方の変化、ライフスタイルの変化…そんな未来の可能性に対応できる「余白」を残しておくことが大切です。
余白スペースの実例
実例1:変化に強いリビング設計 4.5畳分の余裕を持たせたリビングは、当初は子どものプレイスペースとして活用。子どもの成長後は間仕切りを設置して書斎に変更。在宅勤務が増えた今、大変重宝しているそうです。
実例2:多目的和室の活用 1階に設けた4.5畳の和室は、最初は客間として。その後、お子さんの勉強部屋、さらにはご両親の介護スペースへと用途を変えながら20年以上活用されています。
✅ 建築士メモ:完全な理想を詰めすぎず、伸びしろを残す設計こそプロの仕事。スケルトン・インフィルの考え方を取り入れ、将来の変化に対応できる可変性の高い住まいを目指しましょう。
Q&A:読者からよくある質問
Q. 初めて家を建てる人は、どこを優先すべき?
A. 「日当たり」と「家事動線」は最優先でOK!デザインや素材はあとから調整できても、陽の入り方は土地と設計でしか決まりません。特に、朝の日差しが入る位置、風の通り道、動線の無駄のなさは、長く住むほど重要性を実感するポイントです。
Q. 将来の変化に強い家ってどんな家?
A. 可変性(間仕切り変更・空間転用)を設計に入れておくと、30年後も心地よい家になります。具体的には、構造壁と非構造壁を明確に区分し、将来の間取り変更が可能な設計にすること。また、設備配管を集約しておくことで、水回りの位置変更も容易になります。何より重要なのは、「完璧な家」ではなく「成長する家」を目指す考え方です。
Q. コストと品質のバランスはどう取るべき?
A. 長期的な視点では「住み心地の核」となる部分にお金をかけ、変更可能な部分はセーブするのが賢明です。例えば、構造・断熱・気密・設備配管などの「見えない部分」と、窓の性能や方角は妥協せず。一方、内装材や建具などは将来交換可能なので、予算と相談しながら決めていくとよいでしょう。
実体験コラム:「理想の家」への道のり
「自分の家は、3年かけてプラン練ったっていい」
家づくりは”建てて終わり”ではなく、”暮らしの土台”。僕自身も、将来自分の家を建てるときは、家族会議を何十回もやると思います!でもその過程こそが、「幸せな家」をつくる一番の方法だと思っています。
私が関わったあるお客様は、設計前に1年間、休日ごとに様々な住宅展示場やオープンハウスを巡り、「好きな空間」と「苦手な空間」を徹底的に調査されました。その結果、「南面に大きな窓のあるリビング」「キッチンからの見通しの良さ」「収納の使いやすさ」という3つの核を見つけ、それを中心に理想の家を実現されました。
ただし、ここにも「妥協点」がありました。例えば、当初希望していた無垢材の床は、予算と維持管理の観点から高耐久フローリングに変更。デザイン性の高い照明器具も、将来交換しやすいシンプルなものを選択。こうした「今は我慢して、将来のために残す選択」も家づくりでは大切なことです。
時間をかけてじっくり考えることで、「この家で暮らしたい」という確信が生まれ、完成後の満足度も高くなるのです。
あなたの家づくり体験を教えてください!
家づくりの経験は一人ひとり違うもの。皆さんが「これだけは妥協したくなかった」ポイントや「予想外に重要だった」と感じたことがあれば、ぜひコメント欄や「#私の家づくり体験」のハッシュタグでシェアしてください!
次回の記事で紹介させていただくかもしれません。あなたの経験が、これから家づくりを始める方々の貴重な参考になります!
無料でダウンロード!家づくりチェックリスト
記事を最後まで読んでくださった方へ、「建築士が教える家づくりチェックリスト」をご用意しました。以下のポイントをまとめています:
- 採光・通風確認シート
- 理想の収納プラン表
- メンテナンスコスト計算表
- 生活動線チェックリスト
ダウンロードは[こちら]から!
まとめ
家づくりは「一生に一度」と言われるけれど、だからこそ「妥協しないポイント」は最初にしっかり持っておくことが大事です!
建築士として、そして一人の暮らし手として、”資産にもなり、愛着も湧く家”をつくるには、見た目や広さ以上に、「暮らしの本質」に目を向けるべきだと感じています。
採光と風通し、収納の質、素材選びでの維持費削減、生活動線の工夫、そして余白の設計。この5つのポイントを大切にすれば、家計にも優しく、何十年経っても「この家に住んで良かった」と思える住まいができるはずです。
皆さんの家づくりが、後悔のない素晴らしい経験になることを願っています!
関連記事
- 【保存版】家づくりの失敗を防ぐ10のチェックリスト
- 【20代で建てる家】成功例と後悔例まとめ
- 【建築士の本音】本当に暮らしやすい間取りとは?

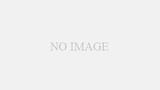
コメント