はじめに
「え、株価20%も下がってる…どうしよう?」 最近の相場変動をニュースで見るたび、心がざわつくことありませんか?
私自身、コロナショック後の2020年終わりに株式投資を始めたばかりですが、この2〜3年で何度か相場の急落を経験しました。資産形成を始めたばかりの方にとって、株価の下落はまるで地震のような衝撃です。でも、本業である一級建築士の視点から気づいたのは、”耐震設計された家”のような資産構造ができていれば、多少の揺れにはビクともしないということ。
この記事では、一級建築士×投資初心者の視点から、株価暴落に動じないための「資産の耐震設計」の考え方を紹介します。私と同じようにコロナ後に投資を始めた方や、将来のための家計管理に不安を感じるすべての方へお届けします!
画像を表示
株価が暴落するのは「想定内の揺れ」
- 株式市場に「暴落」はつきもの 投資を始めて間もない2021年にも、インフレ懸念や金利上昇で急落場面を何度か経験しました。調べてみると、10〜20%の下落は平均して1.5〜2年に1回、30%以上の大暴落も5〜7年に1回は発生しているそうです。これは建築の世界でいえば「定期的に来る地震」と同じだと気づきました。
- 建築で例えると…「震度5強」クラスの地震 建築士として設計時に必ず想定するのが「震度5強〜6弱」の揺れ。株式市場でも20〜30%の下落は「来て当然」と考えるべきなんですね。私も最初は動揺しましたが、今では想定内の出来事と受け止められるようになりました。
- それでも壊れない家には共通点がある 耐震等級3の家が揺れに耐えられるのは、基礎・構造・接合部すべてに「余裕」が設計されているから。資産にも「想定された揺れ」に耐える構造が必要なのです。
【建築士用語解説】耐震等級とは?
建築基準法で定められた耐震性能の格付けです。等級1(標準)から等級3(標準の1.5倍の強度)まであり、数字が大きいほど地震に強い構造となります。資産でいえば、分散度や安全資産の比率が高いほど「耐震等級」が高いと考えられます。
暴落で慌てる人と、動じない人の違い
投資を始めてから知り合った先輩投資家と自分を比較して気づいた違いです:
慌てる人(最初の私)動じない人(目指す姿)短期目線で上がるのを期待長期目線(10年以上)で設計している人気の銘柄に集中投資分散投資でリスクヘッジ済みSNSや友人の情報で売買自分で決めたルールを優先相場の動きを毎日チェック定期的な見直しのみ暴落時に焦って売却暴落時こそ買い増しを検討
- 建築士なら「構造図なしで家は建てない」 耐震性の高い家を建てるには、まず詳細な構造計算と図面が必要です。私が建築の仕事で当たり前にしていることを、投資でもやるべきだと気づきました。
- 投資でも「資産構造図=ポートフォリオ」がカギ 動じない投資家は必ず自分の資産全体を把握し、各資産の役割を理解しています。これは建築の「構造体・非構造体の区分け」に似ています。私も今は毎月資産の全体像を確認する習慣をつけました。
【初心者向け解説】ポートフォリオとは?
投資用語で「資産の組み合わせ」を意味します。株式・債券・現金などをどのような割合で持つかを示すもので、分散投資の基本となります。建築でいえば「構造図」に相当するものです。私も最初は理解できませんでしたが、家の設計図と同じだと考えると腑に落ちました。
「資産の耐震設計」をする5つのステップ
画像を表示
- 資産全体を「構造図」に落とし込む(見える化)
- 総資産の内訳(現金・株・投信など)を一覧表にする
- 建築図面のように「主要構造部」と「二次部材」を区別する
- エクセルやアプリを使って定期的に更新する習慣をつける
- 地盤(生活防衛資金)を固める
- 建物の基礎は地盤の強さで決まる!それと同じで資産の土台は現金
- 最初は低リスクで始め、徐々に投資割合を増やす
- 私の場合、独身なので3ヶ月分の生活費を現金で確保しています
- 柱(長期投資のコア資産)を決める
- 建物の主要構造体となる柱や梁のように、資産の中心となる投資先を決める
- 私の場合は「全世界株式インデックス」をコア資産に選択
- コア資産は総資産の50〜60%を目安に(耐震等級の考え方と同様)
- 耐震ダンパー(分散投資)を設置する
- 現代建築では制震装置が揺れを吸収するように、資産も「揺れ吸収材」が必要
- 国内株・海外株・債券など異なる値動きをする資産に分散
- 私の場合、米国株と日本株、そして少額の金ETFも組み合わせています
- 定期点検(ポートフォリオの見直し)を行う
- 建物の定期点検と同じく、資産も定期的なメンテナンスが大切
- 半年〜年1回の頻度で資産配分を確認し、必要に応じてリバランス
- 私は毎月の積立額は変えず、半年に一度だけ全体のバランスを確認
実体験|投資初心者が学んだこと
私がコロナショック後の2020年12月に投資を始めてから経験した相場変動と、そこから学んだことをお伝えします:
- 2021年初めの好調相場での失敗 高値づかみと銘柄の集中で、一時的に含み損20%を経験。その後リーマンショックや先輩投資家の話を学び、分散投資の重要性を痛感しました。
- 2022年の世界的株安での気づき インフレや金利上昇で世界的に株価が下落。総資産約500万円が一時400万円台まで減少しましたが、毎月の積立は継続。むしろ「セール中」と考え、可能な範囲で買い増しました。すでに配分を決めていたため、感情的な売却を避けられました。
- 現在の資産構成(投資歴3年の私)
- 3ヶ月分の生活費を現金として確保(約20%)
- 全世界株式インデックスが中心(約50%)
- 日本株と米国株(約20%)
- 債券と金(約10%)
まだ投資歴は短いですが、建築士として構造計算の重要性を知っているからこそ、資産設計でも同じ原則を適用できています。暴落時も「設計通りの揺れ」と考えれば、冷静に対応できるようになりました。
画像を表示
よくある質問(Q&A)
Q:現金と株のバランスはどれくらいがベスト?
A:年齢や家族構成、収入の安定性によりますが、投資初心者の私は「現金:投資=4:6」から始めました。建築でいえば「基礎と上部構造のバランス」と同じで、土台がしっかりしていないと上物も危険です!独身の方は最低3ヶ月分、家族持ちなら6ヶ月分の生活費を現金で持っておくと安心です。
Q:暴落時に”買い増し”するべき?
A:私の経験では、ルールを決めているなら「買い増し=正解」です。事前に”いつ買うか”を決めておきましょう。これは建築で言えば「補強計画」のようなもの。私は「10%下落したら月の積立額を1.2倍に、20%下落したら1.5倍にする」というルールを作りました。実際に2022年の下落時に実行し、結果的に良い買い場になりました。
Q:投資初心者が急に資産を増やすコツは?
A:建築と同じで、急いで作ると危険です!地震に強い家は基礎工事から丁寧に作るように、資産形成も地道な積立が基本。私自身、「毎月の積立額×投資年数÷2」程度を目安に考えています。例えば月3万円の積立なら、3年で約50万円が目安です(あくまで目安で、市場状況により変動します)。
Q:どのくらいの頻度で資産チェックするべき?
A:私の経験では、最初は週1回チェックしていましたが、不安になるだけでした。今は月1回の確認と、半年に1回の見直しだけにしています。建物の点検と同じく、あまりに頻繁なチェックは不要です。日々の値動きをチェックすることは、建築でいえば「毎日クラックがないか確認する」ようなもので、むしろ不安を増幅させるだけです。
まとめ
株価が暴落しても、資産全体に「設計思想」があればブレません。建築士として耐震設計の原則を知っているからこそ、投資初心者の私でも”耐震資産設計”を取り入れることで、相場の荒波に動じない資産形成ができるようになりました。
一軒の家を建てるとき、基礎工事から上棟まで段階を踏むように、資産形成も焦らず慌てず、地に足をつけて積み上げていきましょう!
画像を表示
関連記事
準備中!
免責事項:本記事は投資の勧誘や特定の金融商品の推奨を目的としたものではありません。投資は自己責任で行ってください。過去の実績は将来の運用成果を保証するものではありません。

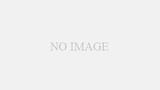
コメント