はじめに
「家計を一緒に管理しているけど、投資ってどう始めればいい?」 「夫婦で方向性が違って、なかなか進まない…」
こんな悩みを抱えているご家庭は多いですよね。共働き世帯や子育て世帯が将来に備えて「投資」を考えるのは自然な流れです。しかし、夫婦間で価値観やリスク許容度にズレがあると意外な落とし穴になることもあります。
この記事では、「住まい=人生最大の資産」に携わる建築士として、そして一人の資産形成実践者として、夫婦で投資を始める際に気をつけたいルールを整理します。家計全体で投資戦略を考えるヒントもお伝えします!
夫婦で投資を始める前にすり合わせておくべきこと
1. 目的を共有する
まずは投資の目的を明確にしましょう!教育資金?老後資金?それともFIRE(早期リタイア)?
目的によって選ぶべき商品やリスク許容度も変わります。例えば:
- 教育費:短期〜中期の安全運用(債券ファンドなど)
- 老後資金:中長期運用(株式インデックスファンドなど)
「家づくり」や「ライフプラン」とセットで考えることで現実的になります!
2. リスク許容度の確認
お互いの性格やお金への考え方からリスク許容度を話し合いましょう。例えば:
- 夫:積極運用(株式中心)
- 妻:安定運用(債券中心)
合意点を見つけることで、お互い納得感ある運用が可能になります。
3. 役割分担と管理方法を決める
夫婦間で役割分担も重要です。例えば:
- 夫:運用担当
- 妻:記録・チェック担当
毎月1回「夫婦お金会議」を設けて進捗確認・振り返りするとモチベーションも維持できます!

夫婦投資のおすすめスタートプラン
1. つみたてNISAで”分散+長期”を
つみたてNISAは初心者にも最適!2024年からは年間120万円まで非課税枠があります。少額から始められるので安心です。
- おすすめ商品:インデックスファンド(例:全世界株式や日米株式)
- 目安:月3〜10万円ずつ積み立ててもOK
長期・分散・積立でコツコツ育てる王道プランです!
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)も活用
節税効果大!掛金は所得控除されます。ただし60歳まで引き出せないため、「生活防衛資金」とバランス調整しましょう。
3. 子どもの教育費は「学資保険」や「特定口座」で分担
教育費は目的に合わせた運用がおすすめ。目的別に口座や運用先を分けることで管理しやすくなります。
※注意:ジュニアNISAは2023年末で終了しました。教育資金は一般NISA枠や特定口座での運用を検討しましょう
建築士×資産形成の視点:住まいと投資はセットで考える
家は固定資産=守るべきもの。一方、投資は育てるもの。この2つをどう両立させるかがカギです。
例えば:
- 「住宅ローン金利2% vs 投資利回り5%」なら投資優先も検討可能
- 家計全体でバランスよく判断することが重要です!
「家」と「お金」を一体として考えることでブレなく進められます!

Q&A:よくある疑問
Q. 夫婦で収入差がある場合、同じ金額ずつ投資した方がいい?
A. 金額ではなく収入比率や生活費負担割合に応じて配分する方法がおすすめです。ただし、資産形成はパートナーシップの問題でもあるため、お互いが納得できる方法を話し合いましょう。
Q. 妻(または夫)が投資に反対している場合、どうすれば?
A. 無理に説得せず、「家計シミュレーション」や「つみたてNISA」の仕組みと数字で対話することがおすすめです。少額からスタートし、成果を共有していくことで理解が深まることも多いです。
実体験:夫婦で投資に取り組んでよかった話
ある共働き夫婦では月5万円ずつつみたてNISA開始。また教育費には特定口座での積立投資を導入。「夫婦お金会議」で家計改善額20万円増加&運用益5万円達成!特に大きかったのは、お金の話をオープンにすることで夫婦のコミュニケーションが活性化したこと。お互いの将来像や価値観を共有する良いきっかけになりました。
まとめ
- 目的共有・リスク感一致・管理方法決定が成功のカギ!
- 無理なく始められる制度からスタートすると安心
- 「住まい」と「お金」をセットで設計する視点が重要
お金の話題は日常会話から始めてみませんか?夫婦で未来を描きながら、一歩ずつ進んでいきましょう!
関連記事
NISAやiDeCoの違い、ちゃんと理解してますか?夫婦での運用に大きく関わる部分です
【2025年版】NISAとiDeCoの違いを徹底解説!初心者でもわかる選び方ガイド
夫婦で投資を始めるなら「確定申告の仕組み」も早めにチェック!
投資初心者向け 確定申告の超基本|建築士が解説!申告の必要なケースと見落としがちなポイントとは?
資産形成は“投資だけ”では成り立ちません。夫婦での貯金目安はこちら

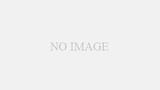
コメント