はじめに
マイホームの購入は、多くの人にとって人生最大の買い物です。しかし、夢と現実のギャップに悩む方も少なくありません。「こうしておけばよかった」という後悔を減らすためには、先人の経験から学ぶことが大切です。
私は建築士として10年以上、住宅設計に携わりながら、同時にファイナンシャルプランナーとしてクライアントの資産形成をサポートしてきました。その経験から、家づくりにおいて「住まいの質」と「資産価値」の両面を考慮することの重要性を痛感しています。
今回は、多くの施主さんから聞いた後悔ポイントと、それを回避するためのアドバイスをお伝えします。これから家づくりを始める方はもちろん、リフォームを検討している方にも参考になる内容です。

間取りに関する後悔ポイント
1. 将来の生活変化を考慮していない間取り
よくある後悔:「子どもが独立した後、部屋を持て余している」「高齢になって階段の上り下りが辛くなった」
解決策:
- 可変性のある間取りを検討する(将来、壁を取り払って広い空間にできるなど)
- 将来的なライフステージの変化を想定した設計
- 1階にも寝室やバスルームを確保する
- 二世帯住宅を検討する場合は、完全分離型か部分共有型かを慎重に判断する
資産形成の視点:間取りの汎用性は将来の売却や賃貸時の価値に直結します。特殊すぎる間取りは売却時に不利になる可能性があります。
2. 収納スペースの不足
よくある後悔:「物が増えて収納場所がなくなった」「クローゼットが使いづらい」
解決策:
- 収納は多すぎることはない(特に日用品のストックやシーズン物の保管場所)
- 使用頻度に合わせた収納計画
- デッドスペースを活用した収納の工夫
- 将来的な物の増加を見越した設計
資産形成の視点:十分な収納スペースは物件価値を高める重要な要素です。特に都市部では収納の充実した物件の人気が高まっています。
設備・インテリアに関する後悔ポイント
1. キッチンの仕様や配置
よくある後悔:「作業スペースが狭い」「動線が悪く料理が効率的にできない」「設備のグレードを下げたら使いづらかった」
解決策:
- 家族の料理習慣に合わせたキッチンレイアウト
- 作業スペースは十分に確保する
- 収納や調理器具の使用頻度を考慮した配置
- コストカットするなら目に見える部分よりも、見えない部分で
資産形成の視点:キッチンは住宅の中で最も高額な設備です。10〜15年で劣化・陳腐化するため、将来のリフォーム費用も考慮した予算配分が望ましいでしょう。
2. 照明計画の不備
よくある後悔:「部屋が暗い」「スイッチの位置が使いづらい」「後から照明を追加するのが難しい」
解決策:
- 間接照明も含めた多層的な照明計画
- 生活動線に合わせたスイッチ配置
- 将来の家具レイアウト変更も想定した配線計画
- LED照明の色温度にも注意を払う
資産形成の視点:適切な照明計画は省エネにも繋がり、長期的な光熱費削減効果があります。初期投資を惜しまないことで、ランニングコストの削減が可能です。
住宅性能に関する後悔ポイント
1. 断熱・気密性能への投資不足
よくある後悔:「夏は暑く冬は寒い」「結露がひどい」「想定以上に光熱費がかかる」
解決策:
- 断熱材は予算内で最高グレードを選ぶ
- 窓の性能(複層ガラス、Low-E等)にもこだわる
- 気密測定の実施を依頼する
- 換気システムとのバランスも重要
資産形成の視点:高断熱・高気密住宅は、光熱費削減効果に加え、将来の省エネ住宅への規制強化を見据えると資産価値の維持にも有利です。初期投資と長期的なランニングコスト削減のバランスを考えましょう。
2. 耐久性・メンテナンス性への配慮不足
よくある後悔:「外壁の塗り替えが想像以上に高額だった」「設備の修理・交換費用が予想外」
解決策:
- メンテナンス頻度と費用を事前に確認する
- 耐久性の高い外装材を選ぶ
- 将来のメンテナンスのしやすさも考慮した設計
- 長期修繕計画を立てておく
資産形成の視点:住宅の維持管理費用は30年間で建築費と同等かそれ以上になることも。将来のキャッシュフローを圧迫しないよう、メンテナンスコストを含めたライフサイクルコストの視点で検討することが重要です。

資金計画に関する後悔ポイント
1. 予算オーバーのスパイラル
よくある後悔:「少しずつグレードアップしているうちに予算をオーバーしてしまった」「ローンの返済が想像以上に厳しい」
解決策:
- 最初に総予算の10%程度は予備費として確保
- 優先順位を明確にしておく
- 将来リフォームできる部分と最初から妥協できない部分を区別する
- 住宅ローンの返済負担率は25%以下を目安に
資産形成の視点:住宅購入後も教育費や老後資金など他の資産形成が必要です。無理のない返済計画で、将来の資産形成余力を残しておきましょう。
2. 将来の売却価値を考慮していない
よくある後悔:「転勤になったが売却価格が思ったより低かった」「リセールバリューを考えていなかった」
解決策:
- 立地の将来性を重視する
- 過度に個性的な仕様は避ける
- 汎用性の高い間取りを心がける
- 省エネ性能など将来価値が高まる要素に投資する
資産形成の視点:住宅は「住む」機能だけでなく「資産」としての側面も持ちます。特に転勤の可能性がある方や、将来的なダウンサイジングを考えている方は、売却時の価値も意識した家づくりを心がけましょう。

Q&A:建築士×ファイナンシャルプランナーの視点から
Q1: 住宅予算の理想的な配分比率はありますか?
A: 土地:建物=4:6が一般的ですが、立地によって変わります。また、建物内では構造・断熱などの基本性能に40%、設備・内装に40%、外構・その他に20%の配分が理想的です。ただし、10年後、20年後のリフォーム費用も考慮した長期的な資金計画が重要です。
Q2: 住宅ローンを組む際に気をつけるべきポイントは?
A: 金利タイプ(変動vs固定)だけでなく、繰り上げ返済の柔軟性、団体信用生命保険の保障内容、金利優遇条件なども比較しましょう。また、住宅ローン控除だけでなく、各種減税制度(省エネ住宅、長期優良住宅など)も活用すると、長期的な負担軽減になります。
私の実体験:後悔から学んだこと
私自身、7年前に注文住宅を建てましたが、収納計画の甘さに後悔しました。特に、玄関周りの収納が不足し、靴や外出用の小物が溢れるように。結局3年後に玄関の改修工事を行い、追加費用がかかってしまいました。
また、キッチンの作業スペースが狭いことも悩みの種です。料理好きな私にとって、まな板と調理器具を並べるスペースがもう少しあれば…と日々感じています。
これらの経験から、クライアントには「日常の小さな動作」をイメージした間取り検討の重要性を伝えています。図面上ではなく、実際の生活動線で考えることが大切です。
専門家との相談方法
家づくりは専門的な知識が必要な作業の連続です。専門家とのコミュニケーションを効果的に行うことで、多くの後悔ポイントを回避できます。
1. 効果的な相談の進め方
ポイント:
- 建築士やデザイナーとの定期的なミーティングを設定し、進捗確認と課題解決を行う
- 相談内容は事前にリスト化し、優先順位を明確化することで効率的なコミュニケーションが可能になる
- 過去の成功例や経験者から得た情報も共有することでアイデアが広がる
資産形成の視点:専門家への相談費用は決して無駄ではありません。適切なアドバイスにより、将来の大きな出費や価値低下を防ぐことができます。
2. リスク管理と柔軟性の確保
ポイント:
- 家づくりでは予算超過や施工遅延など予測不能なリスクが発生する可能性があります
- これらに備えるため、予備費確保や契約書内容確認(例:施工期間延長時の対応)などを徹底しましょう
- 計画変更が必要になった場合でも柔軟に対応できるよう、専門家との密な連携を心掛けましょう
資産形成の視点:リスク管理は資産防衛の基本です。予期せぬ追加費用が発生しても家計が破綻しないよう、適切な資金計画を立てておくことが重要です。
まとめ:失敗しない家づくりのポイント
家づくりで後悔しないためには、以下の3つのバランスと2つの姿勢が重要です:
- 「今の生活」と「将来の変化」のバランス 現在の家族構成や生活スタイルだけでなく、10年後、20年後の変化も想定した計画を。
- 「住まいの質」と「資産価値」のバランス 自分たちの好みを反映しつつも、将来の売却や賃貸も視野に入れた汎用性も大切です。
- 「初期コスト」と「維持コスト」のバランス 建築費だけでなく、光熱費や修繕費などのランニングコストも含めた総コストで考えましょう。
- 専門家との協働姿勢 建築士、インテリアデザイナー、ファイナンシャルプランナーなど複数の専門家の知見を積極的に取り入れる姿勢が重要です。
- リスクへの備えと柔軟性 計画通りに進まないことを前提に、予備費の確保や代替案の準備など、リスクに対する備えを怠らないことが大切です。
専門家の知見を活用しながら、長期的な視点で家づくりを進めることが、後悔のない住まいへの近道です。そして何より、家づくりのプロセスを楽しむ気持ちを忘れないでください。
関連記事
住みやすい家をつくるには「よくある後悔」も先回りで知っておくのが正解!
家づくりに失敗したくない人が知るべき「よくある後悔ポイント」
間取りや設備にこだわるほど、費用バランスも大切です
建築士が語る!理想の家をつくるために必要な費用とは?|予算設計から資産形成まで徹底解説
家を建てる前に知っておきたい“ライフステージ別の資金設計”はこちら

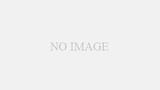
コメント