はじめに
不動産や建築に関わる人なら、一度は耳にする「都市計画法」。とくに宅建試験では毎年のように出題される、超重要な法律のひとつです。
でも、「言葉が堅くてとっつきにくい…」と感じる方も多いのでは?この記事では、現役の一級建築士として、都市計画法の役割や全体像をわかりやすく解説しつつ、家づくりや土地選び、資産形成にもどう関わるのかをお伝えします。
この記事を読むことで、都市計画法の基本概念を理解し、不動産取引や宅建試験対策に役立つ知識が身につきます。さらに、実際の土地選びで失敗しないためのポイントも紹介していきますので、ぜひ最後までお読みください!

都市計画法ってなに?
一言で言うと…「未来のまちをどうつくっていくか」を決めるための法律です。
都市計画法の目的は以下の通り:
- 快適で安全な都市をつくる
- 計画的な土地利用を進める
- 災害に強く、無秩序な開発を防ぐ
つまり、家もマンションも工場も、「どこに・何を・どう建てられるか」は、この法律で”地域ごとに”決められているということなんです。
具体的には、次に説明する3つの基本キーワードを理解することで、都市計画法の全体像がつかめるようになります。
✅都市計画法とセットで知っておきたい「用途地域」についてはこちら
建築基準法の用途地域とは?|土地選びで後悔しないための基本知識
都市計画法の3つの基本キーワード
①都市計画区域
市街地の整備・開発を行うエリアのこと。ここが法律の対象エリアとなります。大きく3種類に分かれます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 市街化区域 | 今後10年以内に優先的に整備する地域(家やお店を建てやすい) |
| 市街化調整区域 | 原則として開発NG(例外はあるが厳しい) |
| 非線引き区域 | 都市計画区域だが、整備の優先順位が未定 |
➡ 市街化調整区域に家を建てようとすると、大きな制約がかかるので要注意!
②用途地域
建築基準法でも解説した「どんな建物を建てていいか」のルール。都市計画法の中で用途地域も定められています。(例:住居系、商業系、工業系の13地域)
➡ 静かな住宅街にパチンコ店が建たないようにする仕組みでもあります。
用途地域の詳細については「用途地域とは?土地選びで絶対に知っておくべき13区分」の記事もご参照ください。
③開発許可
たとえば、広い土地を分筆して宅地化する・道路を新設する場合などは、地方自治体からの「開発許可」が必要になります。
➡ 無許可で開発した土地には建築許可が下りないこともあるので、購入前のチェックが大切です。
開発許可が必要となる主な基準:
- 市街化区域内:1,000㎡以上の開発行為
- 市街化調整区域:原則としてすべての開発行為
- 非線引き都市計画区域:3,000㎡以上の開発行為
これら3つのキーワードをしっかり押さえることで、宅建試験対策としても実践的な土地活用の知識としても役立ちます。では次に、宅建試験での出題傾向を見ていきましょう。
宅建試験ではどう問われる?
宅建試験では、以下のような形式で出題されます:
- 市街化調整区域に家を建てることができるか?
- 用途地域の指定がない地域での建築制限は?
- 開発許可が必要となる敷地面積の基準は?(1,000㎡ or 3,000㎡など)
特に近年の傾向として、単純な暗記問題だけでなく、「具体的な事例における判断」を問う問題が増えています。例えば:
「AさんがX市の市街化調整区域内の土地で分家住宅を建築しようとする場合、どのような条件を満たせば許可されるか」
といった実践的な内容です。
過去問や模試でよく出る「定番テーマ」なので、都市計画法の”基本3点セット”は確実におさえておきましょう!
宅建試験の対策については、基本知識の理解に加えて、過去問演習で出題パターンを把握することが重要です。次に、実生活での都市計画法の重要性について見ていきましょう。
建築士×資産形成の視点から見る都市計画法
土地や建物は、「どこにあるか」で資産価値が大きく変わります。この”どこに”を決めているのが都市計画法です。
例えば…
- 市街化区域で用途地域が明確 → 将来的な売却や活用がしやすい土地
- 市街化調整区域や非線引き区域 → 住宅建設に制限が多く、資産価値が安定しにくい
➡ “この土地、安いな”と思ったら、まずは都市計画法で制限を確認しましょう。
不動産は「価格」だけじゃなく、「法規制」までセットで考えることが大切です。
資産形成の視点から見た都市計画区域
| 区域区分 | 価格傾向 | 資産価値の安定性 | 活用の自由度 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域(住居系) | 高い | 最も安定 | 住居用途に限定 |
| 市街化区域(商業系) | 非常に高い | 景気に左右される | 多様な活用が可能 |
| 市街化区域(工業系) | やや低め | 地域発展に左右される | 工場・倉庫などに有利 |
| 市街化調整区域 | かなり安い | 不安定(規制緩和に期待) | 非常に限定的 |
| 非線引き区域 | 中〜低 | 開発動向に左右される | 自治体によって異なる |
市街化区域内で用途地域が明確な土地は資産価値が安定しやすい傾向があります。特に住居系の用途地域では、将来的な環境の大きな変化が少ないため、資産価値が保たれやすいでしょう。
一方、市街化調整区域の土地は確かに安価ですが、それは「建物が建てられない」という制約があるからです。逆に言えば、将来的に規制緩和があれば、価値が上昇する可能性もあります。調整区域や非線引き区域は規制緩和による価値上昇も期待できますが、リスクも伴います。
長期投資の視点では、自治体の都市計画マスタープランを確認し、都市の発展方向性を見極めることが重要です。エリアの将来性を見越した土地選びが、資産形成の成功につながります。
✅ 都市計画の知識を“失敗しない土地選び”に活かすならこちら
失敗しない土地選びのポイント|建築士が教えるマイホームの土台の選び方

Q&A:よくある質問
Q. 調整区域の土地って絶対に家を建てられないの?
→条件付きで可能なケースもあります。主な例外規定は以下の通りです:
- 農家の分家住宅(農家の子が独立して建てる住宅)
- 既存集落内の自己用住宅(一定の条件を満たす場合)
- 地区計画が定められた区域内
- 公共移転による住宅
- 既存宅地制度による住宅(自治体により取扱いが異なる)
ただし自治体ごとにルールが違うため、必ず事前に役所か専門家に確認しましょう!
Q. 市街化区域でも制限があることはある?
→あります。たとえば「第一種低層住居専用地域」は3階建てがNGな場合も。また、地区計画や建築協定などの上乗せ規制が設けられている地域も少なくありません。“建てられる”=”好きに建てられる”ではないという点に注意しましょう。
Q. 都市計画法の制限は将来変わることがある?
→はい、変わる可能性があります。特に以下のような場合に変更されることがあります:
- 市町村合併による見直し
- 大規模再開発計画の実施
- 都市計画マスタープランの改定
- 人口減少に伴う市街地縮小計画(コンパクトシティ政策)
土地の長期保有を考える場合は、自治体の「都市計画マスタープラン」を確認し、将来の方向性を把握しておくことをおすすめします。
実体験:土地選びの落とし穴
過去に、調整区域の土地が格安で売り出されていて、「夢のマイホームが建てられるかも!」と興奮したお客様がいました。
調べてみたら、開発許可が下りない区域で建築NG。買っていたら、大きな損失になるところでした。
➡ 安い土地こそ、「なぜ安いのか」を都市計画法の視点で見極める必要があります。
土地購入時のチェックリスト
このような失敗を防ぐために、土地購入前には必ず以下の点を確認しましょう:
- 都市計画区域:市街化区域か調整区域か
- 用途地域:希望する建物が建てられるか
- 開発許可:既に許可済みかどうか
- 接道義務:建築基準法上の道路に2m以上接しているか
- インフラ状況:水道・下水道・ガスなどが利用可能か
特に安価な土地には「なぜ安いのか」を慎重に確認してください。「分譲地」と称して売り出されている土地でも、必ずしも建築可能とは限りません。不動産業者の説明を鵜呑みにせず、自分でも市区町村に確認することをおすすめします。
まとめ
- 都市計画法は「まちづくりの基本ルール」
- 土地の価値や使い方を左右する法律で、家づくりにも投資にも直結
- 宅建試験では、都市計画区域・用途地域・開発許可を重点チェック
- 土地購入前には必ず都市計画法上の制限を確認することが重要
建築士からのひとこと: 土地選び・家づくり・不動産投資、どの場面でも都市計画法の知識は活きます。初心者でも、「どこに建てられるか」の視点を持つだけで、判断力はグッと高まります!
資産として長く価値を保つ不動産選びをするためにも、都市計画法の基本をおさえておきましょう。少し難しいテーマですが、この記事の内容を理解すれば、宅建試験対策としても実生活での判断にも役立つはずです。
関連記事
実は“法規制を知らずに後悔”した人、多いんです…

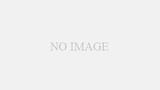
コメント