はじめに
家を建てるとき、よく耳にする「RC造」「S造」「W造」という言葉。でも、実際には「なんとなく聞いたことあるけど、違いはよく分からない…」という方も多いはず。
建物の構造は、見た目では分かりづらいけれど、暮らしの快適さ・安全性・資産価値に直結する重要ポイントです。
この記事では、一級建築士の目線でそれぞれの構造の特徴をわかりやすく解説し、ライフスタイルや資産形成の視点からの選び方も紹介します。

構造の基本「RC・S・W造」って何の略?
- RC造 = Reinforced Concrete(鉄筋コンクリート造)
- S造 = Steel(鉄骨造)
- W造 = Wood(木造)
- SRC造 = Steel Reinforced Concrete(鉄骨鉄筋コンクリート造)
それぞれの構造は「何で支えているか」によって分類されます。どれが良い・悪いではなく、それぞれに向いている用途やライフスタイルがあります。
✅ RC・S・W造の強さを活かすには“耐震等級”のチェックもお忘れなく!
耐震等級とは?建築士が教える”地震に強い家”の見分け方|安心と資産を守る選び方
RC造(鉄筋コンクリート造)の特徴
メリット
- 耐震性・耐火性が非常に高い
- 防音性・断熱性が高く、快適な住環境
- 賃貸・マンション・3階建以上に多く採用される
- コンクリートの高い蓄熱性で夏は涼しく、冬は暖かい
デメリット
- 建築コストが高め(W造より20〜30%高くなることも)
- 工期が長くなる傾向あり(W造の1.5〜2倍程度)
- スラブ(床板)や梁などの構造体を壊せないため、間取り変更などは難しい場合も
メンテナンスと寿命
- 30年程度で外壁の大規模修繕が必要になることが多い
- 適切なメンテナンスで60〜100年の耐久性が期待できる
資産形成視点でのポイント
→資産価値が落ちにくい構造です。特に都市部では人気が高く、売却や賃貸に強いのが特徴です。東京や大阪などの都心マンションでは、RC造が主流であり、築20年を超えても価値が大きく下がらないケースも多いです。「資産になる家」を考えるなら、RC造は有力な選択肢のひとつです。
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)の特徴
メリット
- RC造とS造の長所を組み合わせた、最も強固な構造
- 超高層建築物や大型商業施設、高級マンションに採用される
- 耐震性・耐火性に非常に優れている
デメリット
- 建築コストが最も高い(RC造よりさらに15〜20%高い)
- 工期も長い
- 専門的な施工技術が必要
資産形成視点でのポイント
→長期的な資産価値が最も高い構造と言えます。超高層マンションや都心の高級物件に多く、資産性重視なら検討する価値があります。ただし、一般の戸建て住宅では費用対効果の面でオーバースペックになることも多いので注意が必要です。
S造(鉄骨造)の特徴
メリット
- 軽量鉄骨なら工期短縮・コスト抑制も可能
- 柱の本数が少なく、開放的な空間づくりに向いている
- ビルや商業施設、店舗住宅などに多い
- 大スパン(柱と柱の間隔が広い)の設計が可能
デメリット
- 火災時の強度低下に注意が必要(鉄は熱に弱い特性がある)
- 防音・断熱性はRCほど高くない場合も
- 結露対策が必要な場合がある
メンテナンスと寿命
- 15〜20年程度で塗装やメンテナンスが必要
- 適切な防錆処理・メンテナンスで50〜80年の耐用年数
資産形成視点でのポイント
→二世帯住宅や店舗併用住宅に向いている構造です。収益物件としても活用しやすいのが魅力です。1階を店舗、2階以上を住居にするような用途では、S造の強みが発揮されます。耐用年数も長めで、固定資産として評価されやすいのが強みですね。
W造(木造)の特徴
メリット
- コストが抑えやすく、初期費用が低い(RC造の70〜80%程度)
- 自然素材の温もりを感じやすく、断熱性も優れている
- 間取りの自由度が高く、リフォームしやすい
- 工期が短い(RC造の半分程度)
デメリット
- 耐久性は構造によって差が出やすい(定期的なメンテナンスが必要)
- 防火・防音対策が必要なことも
- 経年による劣化が他の構造より早い傾向がある
工法による違い
- 在来工法(軸組工法):日本の伝統的な工法。設計の自由度が高く、費用を抑えやすい
- 2×4工法(枠組壁工法):北米発祥の工法。耐震性・気密性・遮音性に優れ、工期も短い
- SE構法・木造ラーメン構法:強度が高く、大空間を実現できる木造の新工法
メンテナンスと寿命
- 10〜15年ごとに外壁塗装
- 20〜30年で防腐・防蟻処理や部分的な補修が必要
- 適切なメンテナンスで30〜60年の耐用年数
資産形成視点でのポイント
→コスパよくマイホームを持ちたい人に最適です。建築コストを抑え、その分を資産形成や教育費に回す戦略も可能になります。確かに資産価値の下落率はRC造より大きいですが、初期費用の差を投資に回すことで、トータルの資産形成では逆転できる可能性もあります。
✅ RC造やS造にするとどれくらい費用が変わる?その視点はこちらの記事で
建築士が語る!理想の家をつくるために必要な費用とは?|予算設計から資産形成まで徹底解説
構造別比較表
| 構造 | 主な用途 | 初期コスト | 耐用年数 | 資産価値維持 | メンテナンスコスト |
|---|---|---|---|---|---|
| RC造 | マンション・高級住宅 | 高い | 60〜100年 | ◎ | 中〜高 |
| SRC造 | 超高層マンション・商業施設 | 最も高い | 80〜100年 | ◎◎ | 高い |
| S造 | 店舗併用住宅・商業施設 | 中〜高 | 50〜80年 | ○ | 中程度 |
| W造 | 戸建て住宅 | 低い | 30〜60年 | △ | 頻度高め |

Q&A:よくある質問
Q. 30年後の資産価値を考えるなら、どの構造がベスト?
→立地にもよりますが、一般的にはSRC造>RC造>S造>W造の順で評価されやすいです。東京23区内のマンションではRC造やSRC造が資産価値を維持する傾向があります。ただし、住む目的・ライフプランとのバランスが大切です。初期コストや維持費も含めて総合的に判断しましょう。
Q. 木造でも耐震性は大丈夫ですか?
→近年の木造住宅は**耐震等級3(最高レベル)**が標準になりつつあります。耐震等級とは、建物の耐震性能を示す指標で、等級3は「極めて稀に発生する地震(震度6強〜7程度)でも倒壊しない」レベルを意味します。特に2×4工法や最新の木造工法では、高い耐震性を実現できます。工法や設計次第で、安心できる木造住宅は十分に実現可能です。
Q. メンテナンス費用はどの構造が有利ですか?
→単純な比較は難しいですが、一般的にW造は小規模なメンテナンスを頻繁に行う必要があり、RC造は大規模修繕が数十年ごとに必要になります。W造は外壁塗装(10〜15年ごと)、白蟻対策(5〜10年ごと)などの費用がかかりますが、1回あたりの負担は比較的小さいです。RC造の大規模修繕は費用が大きくなりますが、頻度は少なめです。長期的な資金計画を立てて、メンテナンス費用も考慮しましょう。
✅ RCやS造を選ぶかどうかは“災害リスク”や“資産維持”にも関わってきます
建築士が伝える|災害に強い家づくりの基本とは?防災×資産形成で後悔しない住宅選びを
実体験:僕が構造を選ぶなら?
自分がマイホームを建てるとしたら… 「30代前半:W造で自由な設計+資金を他の投資に回す」 「40代以降:RC造で資産としての強さを意識した家」
というふうに、ライフステージと資産形成の戦略に合わせて構造も選びます。
若いうちは住宅コストを抑えて投資や教育費に資金を回し、ある程度資産ができた段階で資産価値の高い住宅に住み替える戦略も賢明です。
「どれが最強か」ではなく、「今の自分に合った構造は何か」を考えることが大切なんですね。
まとめ
- RC造・S造・W造・SRC造は、それぞれに個性があります
- 建築コスト・資産価値・暮らし方から総合的に選びましょう
- 建築士×資産形成の目線では、構造も人生設計の一部です
- 適切なメンテナンスを計画し、長期的な視点で選ぶことが重要です
家は「暮らしの器」であり、「人生最大の投資」のひとつ。構造を知ることで、納得のいく家づくりと資産形成の両立が可能になります。
関連記事
準備中。

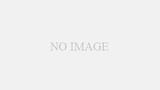
コメント