はじめに
マイホームを持つと避けて通れない「火災保険」と「地震保険」。この2つは【万が一の備え】であると同時に、「資産を守るための大事な戦略」でもあります。
建築士として、これまで数多くの住宅に関わってきた中で「もっと早く知っていればよかった…」という声をたくさん聞いてきました。この記事では、家づくり×お金の視点で、保険の基礎から賢い選び方まで、わかりやすくお伝えします。

火災保険・地震保険ってそもそも何?
火災保険とは?
- 補償範囲:火災だけでなく、落雷、風災、水災、盗難なども対象に
- 建物保険と家財保険の2種類があり、別々に契約するか選択可能
- 住宅ローンを組む場合は、建物への火災保険加入が必須条件となることがほとんど
- 地震による火災でも「地震火災費用保険金」として一定額(保険金額の一定割合)が支払われるケースも
地震保険とは?
- 火災保険とセットでのみ加入可能(単独では加入できない)
- 地震・噴火・津波による損害が対象
- 補償は建物の時価の最大50%まで(建物の再建築費用の全額は出ない)
- 国と民間保険会社の共同運営制度のため、どの保険会社でも保険料は同一
- 損害の程度により「全損・大半損・小半損・一部損」の4区分で保険金が支払われる
火災保険と地震保険の比較表
| 項目 | 火災保険 | 地震保険 |
|---|---|---|
| 補償対象 | 火災、落雷、風災、水災、盗難など | 地震、噴火、津波による損害 |
| 保険期間 | 1~10年 | 火災保険と同じ期間(最長5年) |
| 保険料決定要因 | 建物構造、所在地、保険金額など | 建物構造、所在地(都道府県) |
| 保険金額の上限 | 再建築価額まで設定可能 | 火災保険金額の50%まで(上限5000万円) |
| 割引制度 | 構造級別割引、複数契約割引など | 耐震等級割引(最大50%)、建築年割引(10%)など |
| 保険料控除 | 地震保険料控除の対象外 | 所得税・住民税の「地震保険料控除」の対象 |
建築士目線で考える、保険の重要性

実は「構造」によって保険料は変わる
- 木造と鉄骨・RC造では火災リスクが異なり、保険料に大きな差が出る
- 1981年以降の新耐震基準で建てられた建物は地震保険料の割引(10%)が適用される
- 耐震等級適合証明書があれば最大50%の割引も可能に
- 耐震診断や住宅性能評価で証明書を取得することで、長期的な保険料削減が可能
「修繕できるか」も保険設計のカギ
- 軽微な損害にも備えるべきか、大きな損害のみ対象にするかで保険料が変わる
- 木造住宅と鉄筋コンクリート造では修繕方法や費用が大きく異なる
- 設備や内装材の選択によって、修繕のしやすさや費用も変動
- 免責金額(自己負担額)の設定によって保険料を抑えることも可能
賢い保険の選び方【資産形成の視点で】
補償内容は”必要十分”がベスト
- 手厚すぎる補償は保険料の無駄遣いになりかねない
- かといって必要最低限すぎると、修繕費の自己負担リスクが高まる
- 自分の住まいの特性や地域のリスク(水害頻度など)を踏まえた設計を
- 国土交通省ハザードマップポータルサイトで地域の災害リスクを確認することをおすすめ
建物評価額と保険金額のバランスを見直そう
- 保険金額は「再建築費用」をベースに設定するのが基本
- 築年数が経過しても、修繕・リフォームで資産価値を維持することを考慮する
- 過少申告すると「一部保険」となり、受け取れる保険金が減額されるリスクも
- 家財保険の保険金額は実際の所有物の価値を見積もって設定を(平均的な世帯で300〜500万円程度)
長期一括 vs 年払い、どっちが得?
長期一括払いと年払いの比較例
5年契約の火災保険で比較した場合(仮に年間保険料を5万円と想定):
| 支払い方法 | 5年間総支払額 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 年払い | 25万円(5万円×5年) | 毎年の状況に応じて見直せる | 割引がない |
| 長期一括払い | 20万円(5万円×5年×0.8) | 約20%の割引で5万円お得 | 途中解約で返戻金が減額される |
- 長期一括払いでは最大20%程度の割引が適用される場合も
- 住宅ローンの返済計画や将来の引っ越し予定なども考慮して選択を
- 資金効率を考えると、割引率(約20%)と資金運用利回りの比較も大切
- 住宅取得時の出費が多い時期は年払いの選択肢も
Q&A(実体験ベースでよくある疑問に回答)
Q:どこまで補償すれば安心?
A:実際に台風被害を受けたお客様の例では、風災・水災の補償があったおかげで約300万円の修繕費がカバーされました。地域特性(海沿い、川沿い、土砂災害警戒区域など)や過去の災害履歴から、特に注意すべきリスクを重点的に補償するのがポイントです。国土交通省のハザードマップで自宅の災害リスクを確認してみましょう。
Q:保険会社ってどこがいいの?
A:保険会社選びでは、①保険金支払いの対応スピード、②事故受付の24時間対応の有無、③提携修理業者のネットワーク、④契約後のサポート体制をチェックしましょう。口コミや評判も参考になりますが、自分のニーズに合った会社を選ぶことが大切です。最近では、ドローンによる屋根点検サービスがある保険会社も増えています。
Q:火災保険だけでいいの?地震保険って入るべき?
A:日本は地震大国であり、大地震による被害は火災保険では補償されません。火災保険の「地震火災費用保険金」は限定的な補償(保険金額の5%程度が多い)であり、全額カバーではありません。住宅ローンの残債がある場合や、地震後の生活再建資金が十分でない場合は、地震保険への加入を強くお勧めします。ただし、十分な貯蓄があり、地震リスクの低い地域なら、自己判断で加入しないという選択肢もあります。
Q:耐震等級割引を受けるには?
A:耐震等級割引(最大50%)を受けるには、以下のいずれかの証明書が必要です。
- 住宅性能評価書(新築時)
- 耐震診断結果報告書(既存住宅)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が作成した証明書 取得費用は1〜5万円程度かかりますが、保険料の大幅削減になるため、長期的にはお得になることが多いです。
まとめ
- 火災保険・地震保険は”資産を守る防御力”であり、単なる出費ではない
- 家の構造・立地・ライフスタイルに合わせて最適化することが重要
- 建築士目線で見ると「補修の現実」まで考慮した保険設計が大切
- 高すぎず、足りなすぎず、資産形成とバランスの取れた設計を心がけよう
- 定期的な見直しも忘れずに!リフォームや設備更新後は特に要チェック
- 地震保険料控除(所得税・住民税)の節税効果も忘れずに
役立つリソース
- 国土交通省ハザードマップポータルサイト:自宅周辺の洪水・土砂災害・津波リスクを確認できます
- 耐震等級適合証明書の取得方法:耐震等級による地震保険割引を受けるための証明書取得方法
- 地震保険料控除の申請方法:確定申告や年末調整での控除申請手続きを解説
関連記事
- 【初心者向け】20代から考えるマイホームと保険の話
- 【住宅ローンとセットで見直す】見落としがちな固定費3選
- 【実例あり】RC造の家って地震に強い?メリット・デメリットを解説

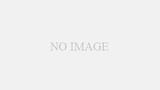
コメント